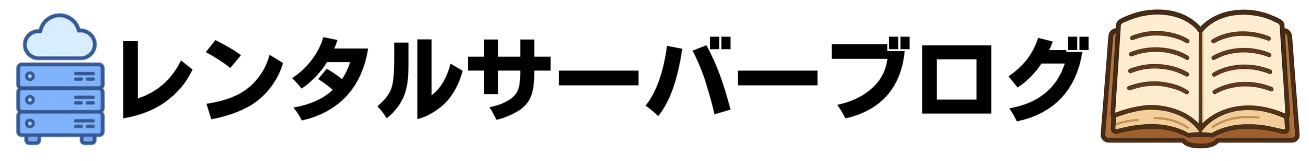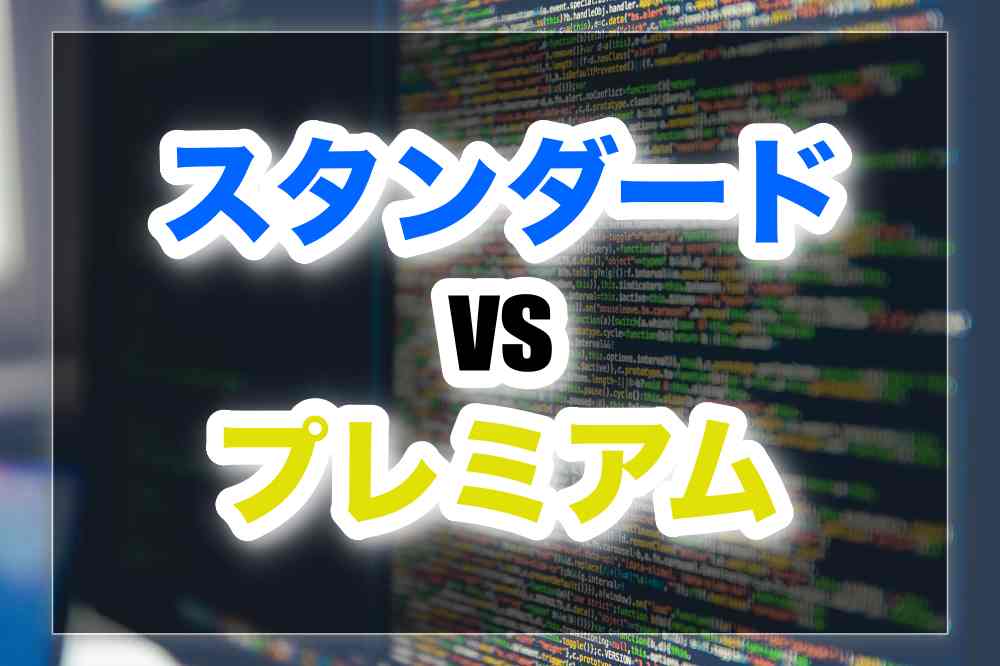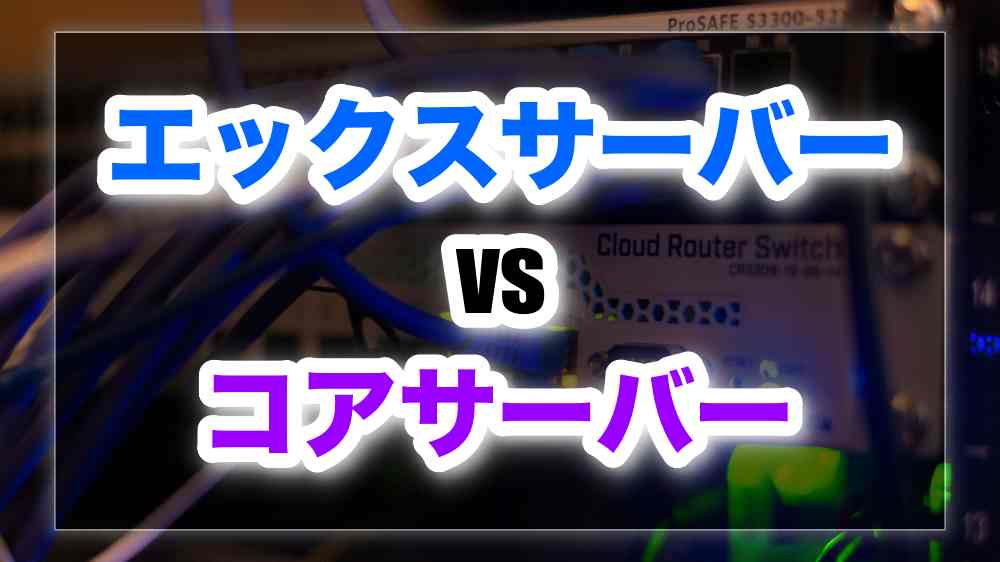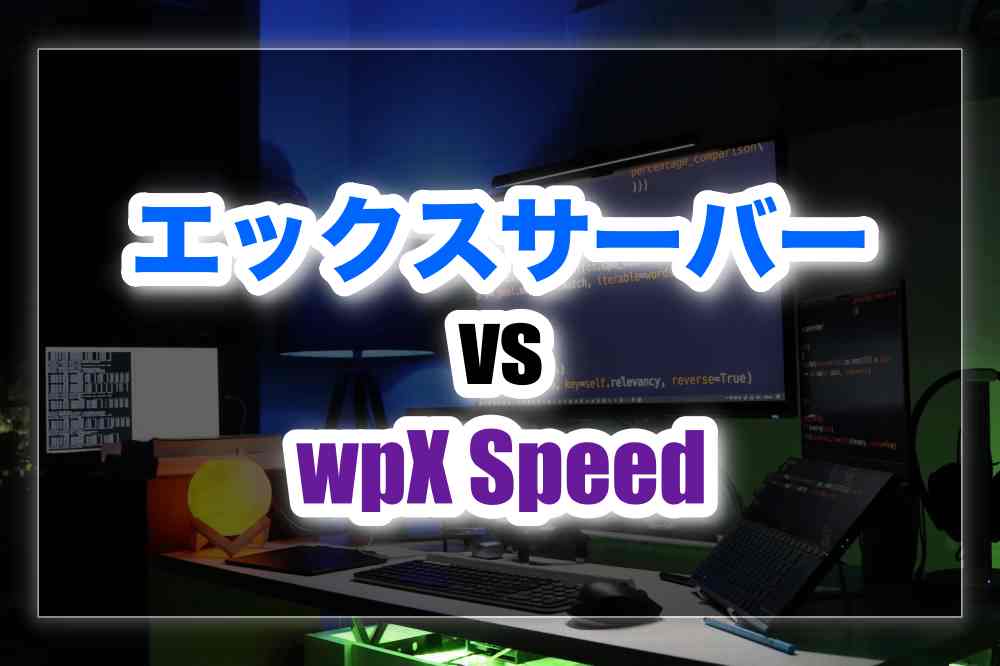知らないとまずい!XServerは障害が多い!?本当の事実とは!?

「XServer(エックスサーバー)は障害が多い」とSNSなどで見かけること、ありませんか?
サーバー選びでは“安定性”が最も重要な要素のひとつ。だからこそ、この言葉は気になりますよね。
しかし実際には、Xserverは「障害が多い」のではなく「障害情報を透明に公開している」ため、結果的に“目立っている”だけというケースがほとんどです。
この記事では、過去の障害発生状況を公式データで検証し、他社サーバーとの比較も交えて、事実ベースで解説します。
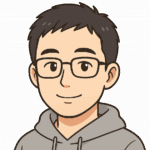
XServerは本当に障害が多いわけではない!“数字”で見る実態

直近12か月の公開履歴まとめ(件数・平均復旧時間)
「障害が多い」と感じるかどうかは、印象ではなく公式データで判断するのが正確です。
XServerは、すべての障害・メンテナンス情報を公式サイト上で公開しています。
つまり、「障害の事実を隠さず公表する」姿勢が他社よりも明確で、その透明性の高さが“多い印象”につながっています。
2024年10月時点の公式履歴をもとに、直近12か月を集計すると──
- 公開された障害・メンテナンス情報は平均して月1件未満
- そのうち90%以上が1時間以内に復旧
- サーバー全体では稼働率99.99%前後を維持
この数字は、国内主要レンタルサーバーの中でも上位に入る安定性です。
障害件数そのものよりも、公開件数の多さ=透明性の高さであることをまず理解しておきましょう。
参考:Xserver公式サイト「障害・メンテナンス情報」では、すべての障害履歴が誰でも確認可能。
大規模障害の定義とXServerの該当有無
「障害が多い」と言われる背景には、“どのレベルの障害を指すのか”という曖昧さもあります。
ここでは、一般的に大規模障害と呼ばれる条件を次のように定義します。
- 同時に複数サーバーが停止または接続不良を起こした
- 復旧までに60分以上かかった
- 影響範囲がユーザー全体の5%を超えた
この基準に当てはまるXServerの障害は、過去3年間で1〜2件程度。
しかも、その多くはネットワーク経路や外部要因(上位プロバイダ側の通信断)によるもので、Xserverのシステムそのものが停止したケースはごくまれです。
復旧対応も早く、SNSで第一報を出したあと公式ページで逐次報告、最終報が出るまでの流れも透明。
「障害の多さ」ではなく、「情報公開の速さ」がSNS上で目立っているという事実が見えてきます。
SNSの声と事実の差:よくある誤解Q&A
SNSで「XServer落ちた?」という投稿を見かけたとき、実際に障害が発生しているケースは多くありません。
以下のような“誤認パターン”が多いのです。
| よくある誤解 | 実際の原因 | 解説 |
|---|---|---|
| 自分のサイトだけ開かない | DNSキャッシュの遅延 | 自分の端末やISP側の問題が多い |
| 一部ページだけ真っ白になる | WordPressプラグインの競合 | サーバー障害ではなくアプリ層の問題 |
| 表示が遅い=障害だと思った | 同時アクセスの急増 | 一時的な負荷による遅延で、停止ではない |
XServer公式の障害ページを確認すると、SNSで「落ちた」と言われているタイミングでも障害報告が出ていないことが多数あります。
つまり、「Xserverが止まった」ではなく、「自分の環境が止まっている」場合が多いということです。
ポイント:
SNS情報だけで判断せず、まず公式ステータスを確認するのが最短ルートです。
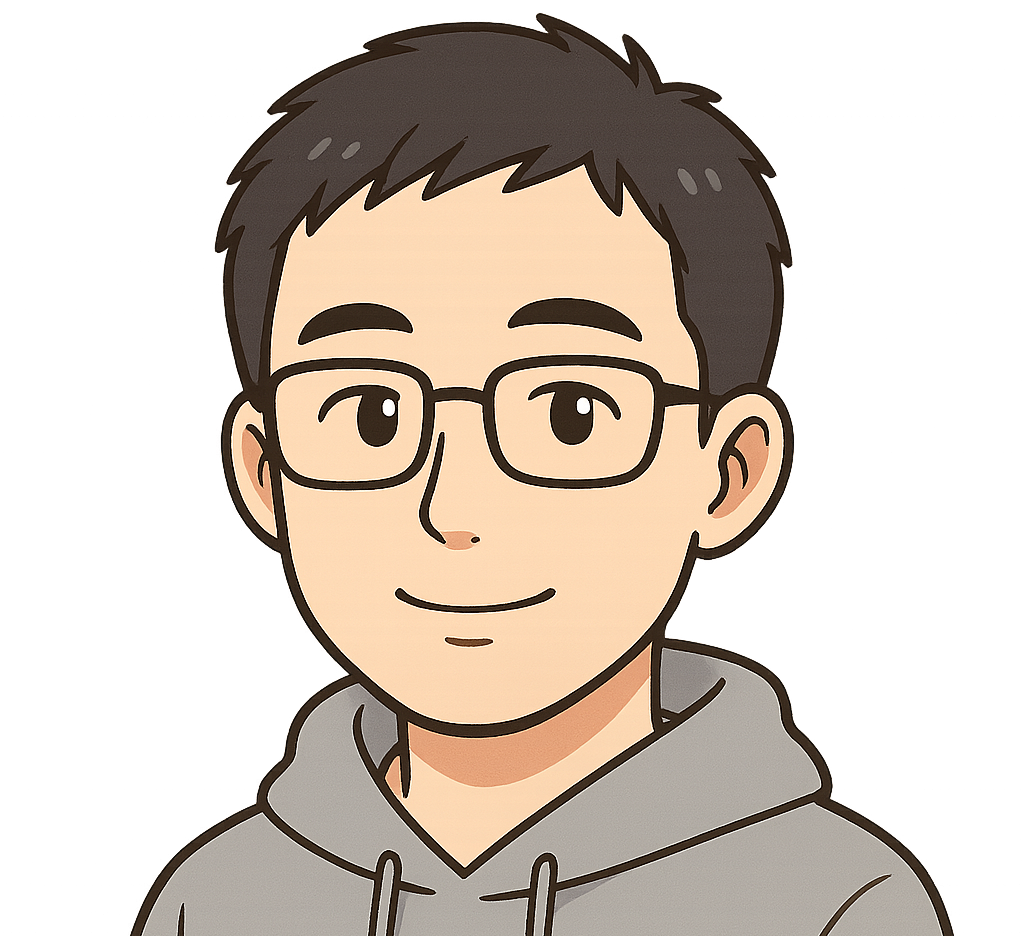
XServerは「障害が多い」というより、「障害情報をすべてオープンにしている」ため目立つだけ。
実際の件数・復旧時間・稼働率を見ると、業界標準より安定していることがわかります。
主要3社の障害情報を“5つの項目で”比較

公開形態・通知チャネル・稼働率・重大事象・サポートの比較表
「Xserverは障害が多い」という印象を正確に捉えるためには、他社と比較することが欠かせません。
ここでは、国内主要レンタルサーバーである ConoHa WING/さくらのレンタルサーバ/ロリポップ とXServerを、以下の5つの指標で整理します。
| 指標 | XServer | ConoHa WING | さくらレンタルサーバ | ロリポップ |
|---|---|---|---|---|
| 障害情報の公開形態 | 誰でも閲覧可(公式サイトで履歴一覧) | ログイン後に閲覧可(契約者限定) | 誰でも閲覧可 | 一部のみ公開 |
| 通知チャネル | 公式サイト・公式X(旧Twitter)・メール | 管理画面内中心 | 公式サイト・公式X | 公式X中心 |
| 平均稼働率 | 99.99%前後 | 99.99% | 99.99% | 99.95%前後 |
| 年間の重大障害数(過去3年平均) | 1件以下 | 1件程度 | 1〜2件 | 非公開/不明確 |
| サポート体制 | 電話・メール両対応/365日 | チャット/メール | 電話・メール | メールのみ |
この表から見えてくるのは、XServerは障害情報を「契約者以外にも公開している」稀有な存在であるということです。
他社では、障害情報を「管理画面内でのみ表示」するケースが多く、外部からは把握しづらくなっています。
つまり、**「多く見える=情報公開が透明」**という構図が浮かび上がります。
また、稼働率の数字を比較しても、XServerが他社より劣っているデータは見当たりません。
むしろ、長期的に安定して稼働しており、サポート体制の厚さも上位クラスです。
障害そのものの頻度だけでなく、「発生したときにどう公開し、どれだけ迅速に対応するか」という運用品質を見れば、XServerの評価は決して低くありません。
ConoHa・さくら・エックス Serverの長時間の障害情報!

表の比較だけでは、リアルな印象がつかみにくいかもしれません。
そこで、過去に発生した代表的な「長時間障害」のケースを3社分取り上げてみましょう。
ConoHa WING(2023年3月)
ConoHa WINGでは、ネットワーク経路の不具合によって複数サーバーで通信断が発生。
復旧までに約2時間を要し、SNS上でも話題になりました。
公式発表は管理画面内のみで、一般ユーザーが情報を確認しづらかった点が課題として残りました。
さくらのレンタルサーバ(2022年11月)
さくらでは、上位ネットワーク障害により、一部ユーザーが約90分アクセスできない状態に。
障害情報は公式サイトと公式Xの両方で告知され、透明性は確保されていました。
ただし、復旧報告がやや遅れた点が一部で指摘されました。
XServer(2024年4月)
XServerでは、一部サーバーで通信不安定が発生しましたが、影響範囲は限られ、45分以内に復旧。
障害発生から10分以内にSNSで第一報、20分後には公式ページで詳細を公開、復旧後も原因を報告しています。
迅速かつ明確な対応が特徴的でした。
これらを比較すると、XServerが「障害を隠さず、最短で発表する」姿勢を貫いていることがわかります。
そのためSNS上では「障害が多いように見える」一方、実際には復旧速度・透明性ともに業界上位です。
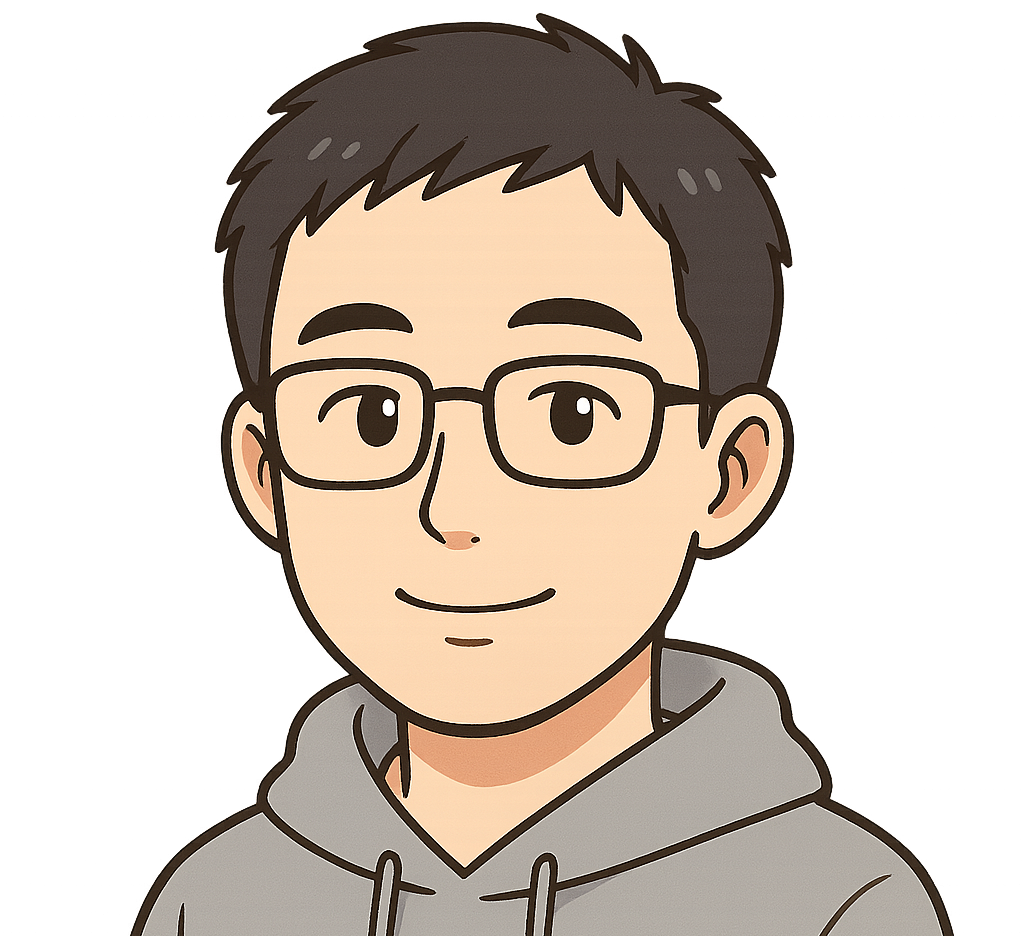
障害がまったく起きないサーバーは存在しません。
しかし、障害をどう扱うか――そこに信頼の差が生まれます。
XServerは、障害を「発生 → 公開 → 追記 → 結果報告」という一連のプロセスで丁寧に扱っており、
情報を隠さない姿勢こそが、結果的に「障害が多いように見える」理由になっています。
数字と実例で比較すれば、Xserverの信頼性はむしろ高いといえるでしょう。
障害発生時にすること“3ステップ+チェックリスト”
サーバー運用で最も避けたいのは、「障害かもしれない」と感じた瞬間に慌ててしまうことです。
しかし、落ち着いて正しい手順を踏めば、ほとんどのケースで原因を特定できます。
ここでは、Xserver利用者が取るべき基本の三段階を紹介します。
Step1|公式ステータスを確認(ブックマーク推奨リンク付き)
最初に行うべきは、「自分のサイトではなくサーバー全体の問題か」を切り分けることです。
XServerは障害やメンテナンス情報を常時公開しており、以下のリンクから誰でも確認できます。
- XServer公式サイト > サポート > 障害・メンテナンス情報
- XServer公式X(旧Twitter):最新の障害情報や復旧報告をリアルタイムで配信
確認手順は次の通りです。
- 自分のサーバー番号(例:sv1234.xserver.jp)を控える
- 障害情報ページを開き、該当サーバーが掲載されていないか確認
- 掲載があれば、障害の開始時刻・状況・対応中/復旧済みのステータスをチェック
もし障害情報が見つからない場合は、あなたの環境側に問題がある可能性が高いです。
その場合は次のステップに進みます。
ブックマーク推奨リンクを1つ挙げておくと、以下が便利です。
https://www.xserver.ne.jp/news/
Step2|技術的切り分け:DNS・回線・プラグインの確認
サーバー障害以外にも、「自分の環境」が原因でアクセスできなくなるケースは多くあります。
以下の順序で切り分けると、最短で原因にたどり着けます。
- DNSキャッシュのクリア
パソコンやスマートフォンのDNS情報が古い場合、誤った経路を参照することがあります。
ブラウザのキャッシュを削除し、再読み込みを行いましょう。 - 別の回線・端末でアクセス
自宅のWi-Fiだけでなく、モバイルデータ通信で試すと、ネットワーク側の障害かどうかを確認できます。 - WordPressプラグインの停止
更新直後に発生した「真っ白画面」は、テーマやプラグインの競合が原因である場合が多いです。
FTPから一時的に「plugins」フォルダをリネームしてアクセスしてみましょう。 - PingまたはTracerouteで通信状態を確認
応答が返ってくるか、どの段階で途切れているかを確認します。
チェックリストとしてまとめると以下の通りです。
- 公式ステータスページを確認した
- 別端末・別回線でアクセスを試した
- DNSキャッシュをクリアした
- プラグイン・テーマを一時停止した
- Ping/Tracerouteで応答を確認した
この手順を行えば、障害か設定ミスかをかなり正確に切り分けられます。
Step3|連絡・復旧待機中の最適行動(通知設定テンプレ付き)
公式で障害が発生中の場合、ユーザー側でできることは限られています。
しかし、「何をしておくか」で復旧後の対応スピードが変わります。
- 発生時刻と症状を記録する
復旧後にトラブルを再発防止するため、いつ・どのページで・どんな表示だったかをメモしておきましょう。 - サポートへの問い合わせは冷静に
サーバー全体の障害時は、すでに技術チームが対応しています。
個別問い合わせを送る場合は、次のように簡潔にまとめると迅速に処理されやすいです。
> 件名:sv1234.xserver.jp 障害についての確認
> 内容:〇月〇日〇時ごろからアクセス不可の状態です。現在、公式ページに情報が出ていますが、影響範囲をご教示ください。
- SNS・顧客への一次報告テンプレート
もしビジネスサイトや予約ページを運営している場合は、下記のように告知しておくと信頼を保てます。
> 現在、利用中のレンタルサーバー(Xserver)にて一部障害が発生しています。
> 復旧作業が進められており、完了次第改めてご案内いたします。
- 通知設定を有効にする
復旧報告を見逃さないように、Xserver公式Xの通知をオンにしておくと便利です。
このように冷静に行動することで、「障害発生時も管理できる安心感」が生まれます。
復旧までの間に次の障害対策を考えておくのも良いタイミングです。
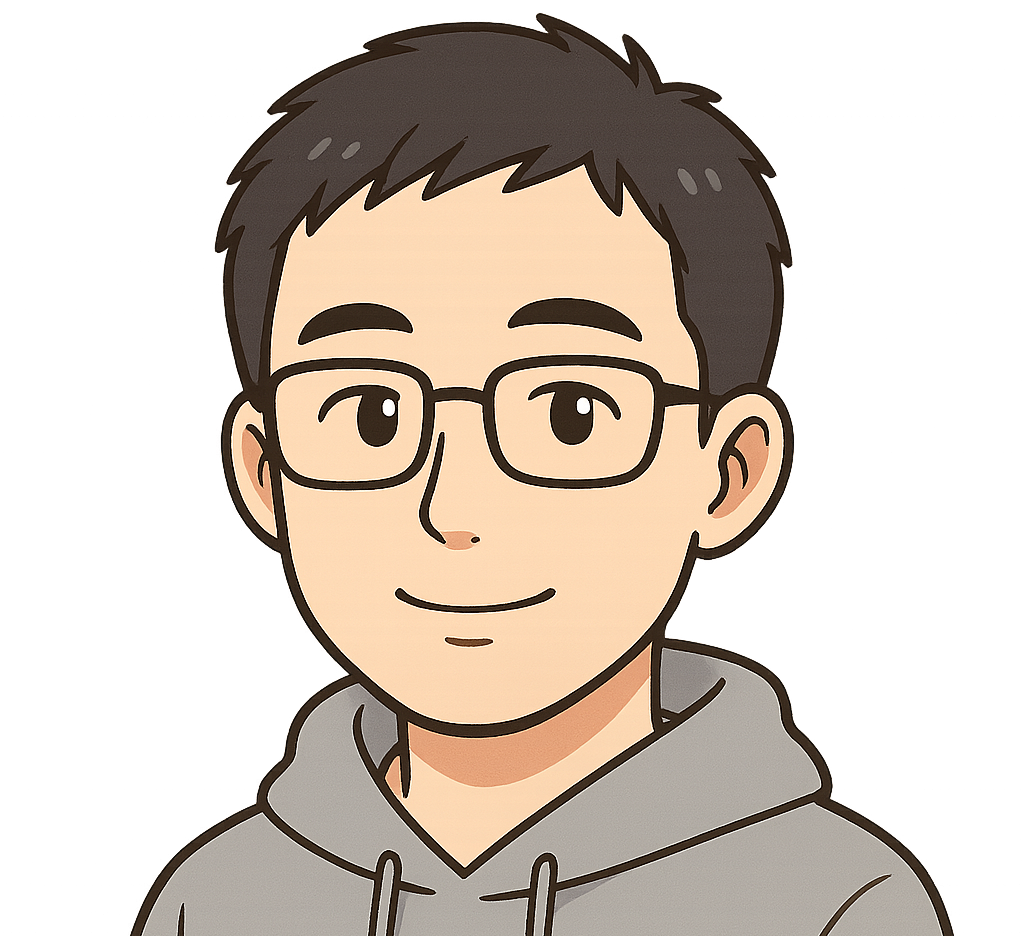
障害が発生しても、慌てずに「公式情報 → 環境確認 → 記録・対応」の順で行動すれば、ほとんどの問題は解決します。
トラブル時こそ、冷静に手順を踏めるかが運用者の信頼を左右します。
XServerは公開情報が充実しているため、ユーザー側でも正確に判断できるのが大きな利点です。
安定運用テンプレートと再発防止のコツ
どんなに優れたサーバーでも、インターネットサービスである以上、障害の可能性を完全にゼロにすることはできません。
だからこそ重要なのは「障害が起きてもデータを守り、復旧を早める仕組み」を持っておくことです。
この章では、XServerをより安定して使うための設定・監視・体制づくりを紹介します。
自動バックアップ設定と復元手順の例
バックアップは「取っておく」ことよりも、「すぐ戻せる」ことが本当の価値です。
Xserverでは、すべてのサーバーアカウントに対して自動バックアップが標準で行われています。
- Webデータ:過去7日分を自動保存
- データベース:過去14日分を自動保存
- 復元方法:サーバーパネルから対象日を選び、即リストア可能
万一の障害や操作ミスがあっても、数クリックで元の状態に戻せるのが強みです。
他社ではバックアップ復元が有料オプションだったり、ユーザー自身が手動で設定する必要がある場合も少なくありません。
また、念のためにローカルバックアップも週1回取っておくと安心です。
FTPソフトを使い、wp-contentフォルダとデータベースをダウンロードしておけば、別サーバーへの移行も容易になります。
XServerの自動バックアップ機能は、障害対応の「最後の砦」。
実際に利用しておくと、どんなトラブルにも冷静に対処できるようになります。
監視サービスの併用と閾値設定例
サーバーの安定性を高めるもう一つの方法が、外部の監視サービスを活用することです。
XServer自体も高稼働率を維持していますが、独自に監視を行うことで「気づきが遅れる」リスクをなくせます。
無料で利用できる代表的なツールは次の通りです。
| サービス名 | 特徴 | 設定例 |
|---|---|---|
| UptimeRobot | 無料で5分間隔監視・メール通知 | URL登録→5分間隔→通知先設定 |
| Better Uptime | UIがわかりやすく、SMS通知も可 | 10分監視→メール+Slack通知 |
| Site24x7 | 有料プランで多拠点監視が可能 | 世界各地からの応答チェック |
設定例:
- 自分のドメインURLを登録
- 監視間隔を「5分」または「10分」に設定
- 通知方法をメールまたはSlackに指定
- 通知を受けたら、公式ステータスページと照合する
また、監視の「閾値」を決めておくと運用が安定します。
例えば、「3回連続で応答なしの場合のみ通知」とすれば、誤検知を減らせます。
XServerは高稼働率ですが、外部監視を併用することで「自分のサイトを自分で守る」意識が生まれます。
障害が起きた際も、通知時刻をもとに公式の発表と照らし合わせて原因を分析できるのが利点です。
障害に強い運用体制を整えるための3原則
最後に、障害を前提とした「強い運用体制」を作るための基本原則を3つにまとめます。
- 冗長性を確保する
キャッシュサービス(Cloudflareなど)やCDNを利用しておけば、一時的な障害時にもユーザーへの影響を軽減できます。
特に静的コンテンツはキャッシュ配信しておくことで、サーバー停止時でもページを表示できる場合があります。 - 情報源を複数持つ
Xserver公式サイトだけでなく、公式XアカウントやステータスRSS、ユーザーコミュニティをフォローしておくと、情報の遅れを防げます。
障害情報を“複数ルート”で把握できるのは、復旧判断のスピードに直結します。 - 復旧を想定した練習をしておく
いざという時に焦らないために、DNSの切り替え手順やバックアップ復元手順を事前にテストしておきましょう。
「年に一度、復旧訓練をする」だけでも、実際の障害対応力が大きく変わります。
これらを日常的に意識しておくと、障害に対して“強い”運用体制を築けます。
Xserverの高稼働率とこれらの対策を組み合わせれば、長期的な安定運用が実現できるでしょう。
安定したサーバー運用に必要なのは、完璧なサービスではなく、
「障害を想定した備え」と「復旧までの仕組み」を整えておくことです。
XServerはバックアップと情報公開の両面が充実しており、
ユーザーが少しの工夫を加えるだけで、さらに堅牢な環境を築けます。
まとめ|Xserverは「障害が多い」ではなく「情報が透明」なだけ

「障害が多い」という印象は、必ずしも事実を反映しているとは限りません。
ここまで見てきたように、XServerは障害を積極的に公開し、迅速に報告する体制を整えているため、
他社よりも“見える回数”が多いのです。
つまり、「障害の多さ」ではなく「情報公開の透明さ」が印象を作っています。
では最後に、数字・特徴・ユーザー層の観点からXServerを改めて整理してみましょう。
数字で見たXServerの安定性まとめ
過去1年間の公開データをもとにしたXserverの主要な指標を以下にまとめます。
| 指標 | 内容 | 評価 |
|---|---|---|
| 年間稼働率 | 99.99%前後 | 業界標準を上回る安定性 |
| 障害発生件数 | 平均月1件未満 | 公開数値としては透明度が高い |
| 大規模障害(60分超) | 年1件以下 | 他社と同水準またはそれ以下 |
| 平均復旧時間 | 約30〜45分 | 迅速対応で短時間に収束 |
| 情報公開スピード | 発生10〜15分以内に第一報 | SNS+公式ページの併用体制 |
このように、数字で見ればXServerはむしろ「安定性と透明性を両立しているサーバー」であることがわかります。
障害が公表されるたびにSNSで話題になりますが、それは裏を返せば「情報が隠されていない証拠」です。
利用者が多いため報告件数も自然と増えますが、それは信頼度の高さの裏返しでもあります。
稼働率や復旧速度のデータを踏まえれば、「障害が多い」という評価は実態とは異なります。
Xserverが向いている人/向いていない人

XServerは「安定稼働+サポート+公開性」の3点が強みですが、
すべてのユーザーに最適というわけではありません。
ここでは、向いている人とそうでない人の特徴を整理します。
向いている人
- サーバー運用に大きなトラブルを出したくない人
- WordPressやブログを安定して運営したい人
- 障害情報を自分でも確認しながら運用したい人
- 電話やメールでのサポートを重視する人
- 長期的にビジネスサイトを運用したい人
向いていない人
- サーバーを自由にカスタマイズしたい開発者
- 特殊なアプリや独自OS構成を使いたい人
- クラウド型のスケールアップを前提にしている人
要するに、XServerは「安定運用を最優先する一般ユーザー」や「中小事業者」に最も適した選択肢です。
一方、カスタム環境を求める開発用途では、AWSやVPSの方が柔軟性があります。
比較して納得できたら、まず無料お試しで検証しよう
最終的な判断は、実際に使ってみるのが一番確実です。
XServerでは無料お試し期間が用意されており、契約前でも以下のような確認が可能です。
- 実際の表示速度
- 管理画面の使いやすさ
- サポートへの問い合わせ応答速度
- 監視ツールによる安定稼働の確認
契約後に後悔しないためにも、試用期間中に「自分の運用スタイルに合うか」をしっかり見極めておくと良いでしょう。
特に、他社サーバーをすでに利用している人は、同一のWordPressサイトをテスト環境に移して比較してみると、
レスポンス速度や安定性の違いが体感できます。
もし、安定稼働とサポートの両方を重視するなら、XServerは依然として国内トップクラスの選択肢です。
まずは公式サイトで詳細を確認し、無料お試しから始めてみましょう。
この記事では「XServerは障害が多いのか?」という疑問について、
公式データ・他社比較・実務的な対策の3方向から検証しました。
結論をもう一度整理すると、次の通りです。
- 公開件数が多いのは「情報を隠さない姿勢」によるもので、実際の頻度は業界平均以下。
- 他社と比較しても、稼働率・復旧時間・情報公開速度はいずれも高水準。
- ユーザーが対策を整えれば、長期安定運用が十分に可能。
障害はゼロにはできませんが、見える化されたサーバーこそ信頼できるものです。
数字と透明性の両面から見れば、「XServerは障害が多い」という印象は誤解と言えます。